Interviews
インタビュー
学生による教員インタビュー

自分の問題意識から
課題を発見する力をつける学び
民俗学・地域研究・文化人類学 和田健 教授
インタビュー日時:2023年1月16日
聞き手:国際教養学部2年 岡野・井澤
自身の専門分野、及び、研究の中心的なテーマを教えてください。
専門は「民俗資料論」「民俗学」になります。民俗というのは「folklore」で、「ethnology(民族)」の方ではないです。古くから伝わっている生活習俗や、今当たり前に私たちがやっている所作や振る舞い、考え方などは、時代によって変わっていく部分がありますよね。1つには、そういったような価値観の変容を見ていくということをしています。もう1つの研究の中心は、農山漁村でフィールドワークをし、社会集団の中での古くからの慣習と、現代的な問題とのせめぎ合いを見て記述していく、いわゆる「民俗誌」を書いていくことです。
その分野を専攻した理由やきっかけはありますか?
柳田國男の「方言周圏論」を聞いたことはありますか?都であった京都が日本の真ん中で、そこで流行った言葉が地方に波紋上に広がっていく。そして、地方に行けば行くほどその言葉が時代を経ても残っていることがある。京都を中心に同心円状に広がるから、東側と西側で似た言葉が残っているという、「本当かいな?」と思うような説なんだけど(笑)高校時代に、初めてその方言周圏論を知った時に、面白いなと思ったのが1つのきっかけですね。あくまでも文化周圏論ではなく言葉や方言がそうやって残っているということなんですけど、そういう仮説を出した見方が面白いなと思いました。
もう1つは、大学の時に僕は考古学を専攻しようと思っていたんですよ。それで、考古学の発掘実習と、民俗学の聞き取り実習の両方に参加していました。そのどちらが面白いかと言ったら、聞き取りの方がやっぱり面白くて。今となって思うのは、20代前後の見知らぬ大学生に、70、80歳代の方が喋ってくれているというのが面白いというか。どう自分のことを分かってもらおうか、お話してくれる方との色々なやり取りを経験していくと「あ、人と話をするのは面白いな」と思って。そういうことで、聞き取りをする民俗学を選んだということですね。
研究者には、いつ頃なろうと考えましたか?
研究者の道に行こうと思ったのは、学部の4年生で、卒業論文を提出する約1ヶ月前(11月頃)ですね。実は、民俗学も面白いのですが農業に関わることの関心が強くて、環境科学系大学院の修士課程を受験しようと思っていたんです。そこを2年で修了して、環境科学に関わる会社か、農業に関わる仕事に関わるのもいいかなと。そう思っていたことを、よく私の面倒を見てくれた民俗学講座の若手の先生に、10月くらいに相談したんです、「進路はそちら(環境科学系の大学院)にしようと思います」って。そしたら、「30分ぐらい時間をもらえないか」と言われて、喫茶店に連れていかれて、滔々と何かを言われて。何を言われたか覚えていないのだけれど、喫茶店を出たときには「わかりました、覚悟を決めて民俗学の大学院に行きます」ってなっていました(笑)その時はじめて、一貫制博士課程の方の受験をしようと思ったので、まさに late specialization なんですよ。
国際教養学部で教育を行うことの面白さ、難しさはありますか。
面白さは間違いなく、色々な専門分野の先生がいるということですね。今まで自分が育ってきた分野の先生たちとは違う付き合い方をしないといけないです。例えば、民俗学や文化人類学の先生たちがいるという構図だったら、自分たちが育った中での人間関係、学説、あるいは考え方の構造がほぼ共通して見られます。ですがこの学部では、全然違う専門領域で育った人と対話をしていかなければいけない。それは妥協をするということではなくて、相手を理解しながら進めていかなければいけないということです。それを苦痛に思う先生もいるかもしれませんが、私は違う分野の人と話をするのは面白いですね。
学生さんも、いい意味で固定観念にとらわれずに学んでいる人が多い。「なぜこうなんだろう」という疑問から入る人が多い。普通だったら「社会学はこう考える」「民俗学はこう考える」ってなりますよね。そんなことは関係なく、まず疑問を深めながら、「そもそもどの学問分野でこの問題を扱っているのか」と、思考を逆にして考えていける。そこは面白いかなと思います。
先生が授業や教育活動の中で重視していることや、意識されていることはありますか。
講義形式の場合は、国際教養学部にはいろんな専門領域に進んでいく学生がいるということを意識しています。例えば、「質的調査法I」という授業では、聞き取りや、相手がいる前提でのデータの収集について学びます。ですが、目の前の学生さんはデザイナーになるかもしれない、建築に関わる仕事をするかもしれない、まちづくりをめざす人もいるかもしれない、あるいは僕みたいなフィールドワークをする文化人類学や民俗学をめざす人もいるかもしれない。そこで、「自分がやっていることを、違う道を行くであろう人に教える中で、何を投げかけられるだろうか」ということをすごく考えるので、自分自身大変だなと思いながらも楽しいです。
また演習や実習では、とにかく「自分でデータを取る方法をどうしようか」ということを一緒に考えます。質的調査もありますが、量的調査でどうするかということも考えつつ、一次資料を取りに行くというのを、学生さんと一緒に考えて、心がけるようにしています。
 持続的地域貢献活動実習での田植え体験
持続的地域貢献活動実習での田植え体験 持続的地域貢献活動実習での菅江縄の縄ない体験
持続的地域貢献活動実習での菅江縄の縄ない体験文系か理系かなど、先生のゼミを希望する学生に求めることはありますか。
この学部そのものが、文系・理系という考え方で教育をしていません。それよりも、自分でデータを取ってくる、そのために学問分野ひとつにこだわらず、どういう方法があるのかということから学ぶことに積極的な学生さんは歓迎ですね。
また、私は「こういうものを研究対象としている人を受け入れる」ということもありません。その学生さん自身が、「この課題(イシュー)に興味があるんです」と明確に言える人が第一です。クロスメジャープロジェクトIIでは、まずは自らの関心に沿ったテーマについて「どのような研究論文があるのかを探してみよう」ということをやります。その後、関心の領域はどの学問で一番研究されているのかを考え、外せない研究者は誰なのかを調べていきます。僕も全部を知っているわけではないので、参考文献リストの中で、この人は外せないんじゃないかとか、最近の研究論考がないのは単純に調べ落としなのか、この研究はある程度の進展度があって、新しい展開を生み出すことができるのかを考えていくんですね。そういったことを、関心を持って深くやってくれる学生さんであれば、研究対象はなんであれ歓迎です。
自身の大学時代についてお聞きします。先生はどのような大学生でしたか。
僕はね、実は高校を出てから社会人をやっていたんですよ。掃除の仕事をやっていて、その後に大学に行ったんですね。だから、自ずと私が年上で、社会人経由で入ってきた人があと2人いて、3人が同じ学年の中で身近なグループでした。大学が寮だったので、よく明け方まで飲みながら話をしていましたね。50代半ばになった今でも付き合いはありますね。
学生に向けて、今やっておいた方が良いと感じることはありますか。
しんどい時は休む、頑張れる時は頑張ると。これをやった方がいいとか、留学した方がいいというよりも、しんどい時は「しんどい」と言えるということを意識してくれた方がいいと思いますね。自ずと体が動いて行動できる人もいる、動かない人もいるでしょう。卒業要件とかあるんですけど、無理なことは無理をしない。しんどい時は「しんどい」と周りに言うということを心がけてくれるといいなと思いますね。
趣味や好きなことはありますか?
大きな趣味はないんですけど、ウォーキングが好きですね。自分が住んでいる近くも歩きますし、そうでないところに電車で行って、ずーっと歩くこともあります。歩く速度で周りの景色を見るのが好きなんですよ。あと歩いていて、飲み屋があったら大体入ってしまいます(笑)
また、隙間時間は本を読んでいます。自分の研究に関連する本、その両脇にある本、小説とか、いろいろ広がっていきます。10分ほどあったとしたら、小説とかを読んでという感じですね。普段の仕事で読まなければいけない本とか研究書、論文とは別のものを読むようにしていますね。
座右の銘はありますか。
後藤新平が言っていた、「財をなすのは下、仕事をなすのは中、人を育てるのが上」ですね。故・野村克也監督が、この言葉がとても好きだったと聞きます。要するに、お金を残すっていうのは下だと、仕事ができるのは真ん中だと、人を育てるのが上だと。今、縁があって大学の教員をやっていますけれど、皆さんが育って、無事社会に出てくれる。そして何年か経って、「あの先生誰だっけ」ってなるぐらい、忘れてもらうぐらいがいいのかなって思いますね(笑)
高校生に国際教養学部をアピールするとしたら、どういった点がありますか。
あえて言えば、「最初から専門を決めていない」「専門は後から決めればいい」という人には向いている学部だと私は思っています。「学部や専門は目的を持って選ばないと」ということに疑問を持てる人がいいかなと。だから「何も決まらないんだよね」とか「決められるわけがない」といった開き直りをしてくれる人なら、国際教養は合うかなとは思いますね。
国際教養学部はどのような人を求めますか。
「自分で決めて、やりたいことをやっていい」ということに耐えられる人。自分で決めたことを、決めた通りにやることを絶対に邪魔しない学部なので、自分でやりたいようにやってもらうと。逆に、「好きにやっていいよ」っていうのが苦痛な人もいるはずなんです。そういう人には、もしかしたら辛いかもしれない。だから、「自分の好きに動いていいよ」っていうのに耐えられる人に来てもらえると、本人も1番幸せかなって思います。
国際教養学部の今後の展開に期待することを教えてください。
学部に関しては、やはり教員同士が対話をしながら成長していく学部であるといいかなと思います。みんな違う専門分野で育ってきたからこそ対話をしないと学部の運営ができないので、やはりそういう対話を続けられる学部組織でありたいです。
学生に関しては、専門を後で決めていいと。やりたいことってそんなに早く決まらないし、決まっていれば幸せだけれど、決まらなくていいんだということを自覚して、学部を卒業してくれるといいかなと思いますね。
1・2年生におすすめの本
宮内泰介・上田昌文(2020)『実践 自分で調べる技術』岩波新書
インタビューの中で、「一次資料を取りにいくことを、積極的にできる人」と言いました。この本では、どの学問領域においても共通して大事になる「一から調べる」という時に、どういう手順で調べていって、どのように分析するか、ということがわかりやすく説明されています。「メジャープロジェクト」の授業の中でもすすめていて、大学1〜3年生の間にこの本を読んでおくとよいと思います。
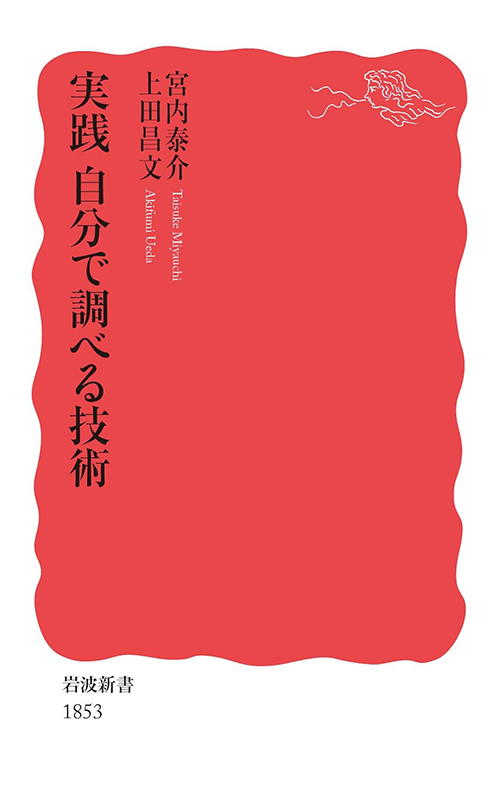
和田 健(わだ けん)
千葉大学大学院国際学術研究院長・国際教養学部長・教授。博士(文学)。
筑波大学歴史人類学系助手、千葉大学国際教育センター、大学院人文社会科学研究科担当などを経て現職。専門は民俗資料論。農山漁村の協同労働・協業関係や、日本人学生、留学生の協同学習に関わる実践的研究などについて研究をついて研究を行う。主な著作に『協業と社会の民俗学 : 協同労働慣行の現代民俗誌的研究』(2012年 学術出版会)『経済更生運動と民俗 : 1930年代の官製運動における介在と変容』(2021年 七月社)など。